News

菌糸・マット交換
虫が蛹室を作り始める時期に、劣化したマットや菌糸ビンを使用していると、羽化不全のリスクも高まります。交換の必要性を感じたら、早めに交換することを心がけて下さい。 《交換の前に》手を綺麗に洗いましょう。人の手には様々な菌がおり、幼虫が好まないものもあるかもしれません。幼虫にはなるべく直接触らず、きれいなスプーンを使うと良いです。 《マット交換》 マットは3ヶ月ぐらいたつと栄養分が減ってきてしまうので、交換の目安にして下さい。マットを新しく入れ替える際は水分調整も忘れずに行います。加湿のしすぎはカビが生えたり、マットの劣化、幼虫の発育不全、病気につながります。幼虫はマットを食べて大きくなる時期とあまり食べない時期があります。頻繁にフンがマット表面に目立ってきているようなら、その幼虫はよく食べて大きくなっている可能性が高いので、フンを取り除いて新しいマットを足して下さい。ほぼフンになっている場合は、古いマットを少し残してマットを新しく交換します。蛹になるまでこれを繰り返します。ケースの大きさやマットの状態を見て判断してみて下さい。 《マット交換が必要な時》 ・コバエが大量に発生した時・線虫が発生した時・カビの発生がひどい時 マットは3ヶ月ぐらいたつと栄養分が減ってきてしまうので、交換の目安にして下さい。また水分のやりすぎは、マットの劣化にも影響します。湿度が高すぎたり、通気性がなかったりすると環境が不衛生になっていきます。 《交換時に幼虫がマットの上に出てきていたら》 幼虫が外の空気を吸いにくることがあります。時間がたっても潜っていかないようなら、マットがフンだらけでエサが不足していたり、マットの劣化や加湿で幼虫が酸欠を起こしている場合があります。エサが足りている場合は、マットをかき混ぜて様子をみて下さい。 菌糸ビン交換 白い部分が3割程度になってきたら交換のタイミングです。菌糸は生き物なので、購入後は2~3ヶ月で使用するようにします。幼虫の大きさやオスかメスかによってボトルの大きさが異なってきます。幼虫の成長に合わせてボトルの大きさを考えてみましょう。 菌糸ビンは生ものですから、まとめ買いはせず、すぐに使用する分だけ購入します。お店では菌糸ビンが劣化しにくいように冷蔵庫に保管されていることがほとんどです。その為、購入直後に幼虫を入れてしまうと急激な温度変化で弱ってしまう場合があります。数時間だと内部はまだ冷たい状態の可能性が高いので、温度が均一になるまで一日以上待ってから幼虫を投入します。

カブクワ飼育・繁殖の流れ
①飼育用品の準備②成虫・幼虫を購入③飼育を始める(エサ交換-水分管理-マット交換など)マットは乾燥に気をつけ、たまに霧吹きをします。幼虫が大きくなれば容器を大きいものに移し替えたり、フンが目立つようになればマット交換をします。④ペアの成虫を交尾(ペアリング)させる成熟度合いを確認。成虫は羽化から2~3週間後が目安。⑤産卵セットを組む用意したマットは手で握ってみて形が崩れない程度の水分量に調節します。マットの下3分の2は固く詰め、上3分の1は柔らかく詰めます。⑥採卵-マット産み早いと産卵セットを組んだ当日から卵を産み始めます。卵から幼虫になる期間は個体温度により異なります。幼虫は産卵セット内のマットを食べて育ちますので幼虫になるまで2~3か月待ってからケースをひっくり返してみるのもよいと思います。⑥割り出し‐材産み産卵木を崩して卵があるか確認します。⑦幼虫飼育、菌糸ビン交換小さい幼虫は1~2齢幼虫、大きい幼虫は3齢幼虫で脱皮を繰り返し大きく成長します。ここでも水分調節に気をつけます。
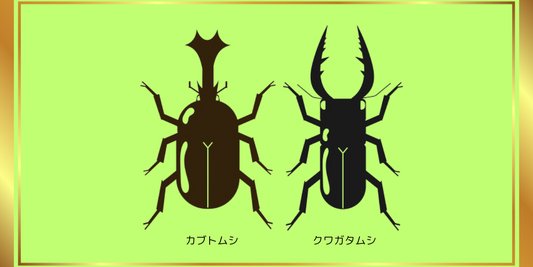
カブトムシ・クワガタムシの飼育の違い
昆虫の飼育は、犬や猫などの哺乳類に比べると簡単で手間もあまり多くはありません。 カブトムシの成虫は、種類に関わらずほとんど同じ飼育環境で飼育することが出来ます。では、どのような用品を用意しておけばいいのでしょうか?カブトムシの成虫の飼育方法についてまとめました。 カブトムシといえば昆虫の王と呼ばれることもありますが、成虫になってからは短命な生き物です。平均寿命は交尾をしたかしなかったかでも異なり、交尾をした場合の方が寿命は短くなります。成熟してからの寿命は種類によっても異なりますが、最もポピュラーな日本産カブトムシなら寿命は2~3ヶ月です。 成虫の飼育に必要なものは飼育容器・飼育床・餌・止まり木の四つです。飼育容器は、種類に合わせて適切な大きさのものを選びましょう。飼育床には広葉樹の完熟発酵マットを使います。餌は基本的に昆虫ゼリーを与えます。止まり木は、引っくり返ったカブトムシがつかまって起き上がるのに使います。10cmくらいの大きな木片を入れてあげましょう。幼虫の飼育では飼育容器と餌が必要です。餌は広葉樹の完熟発酵マットを使ってください。 クワガタムシは、種類によって気性や性質が異なる昆虫です。 温厚で大人しいオオクワガタや、気が荒くてメスを殺してしまうことも多いヒラタクワガタまで、性質は様々です。寿命は長く、オオクワガタなら3年以上生きることが多くあります。ノコギリクワガタ・ミヤマクワガタは比較的寿命が短く、3~6ヶ月ほどの寿命です。 クワガタムシの飼育に必要な用具は、カブトムシとほとんど同じです。一点異なるのは、クワガタムシは木に幼虫を生むため産卵木が必要だということです。産卵木には、キノコ菌などで朽ちかけた木を水でふやかし、ドリルで穴をあけて産卵が出来るようにして入れてあげます。

カブクワの一生
◆初令(一令幼虫)孵化して間もない幼虫は頭が白色をしています。日にちがたつにつれ、頭がオレンジ色に変化していきます。◆2令幼虫初令幼虫は数日後、脱皮をして小さくなった皮ふを脱ぎます。この時期の幼虫を2令幼虫といいます。2令幼虫になってしばらくたつと頭の色が黒っぽくなります。◆3令幼虫(終令幼虫)数週間たち、今度は2度目の脱皮をして3令幼虫となります。3令になると頭部が大きくなるので分かりやすいです。この時期になるとマットや菌糸を沢山食べて大きく成長し、フンも大きくなります。最低3ヶ月に1回程度はマットの状態を確認し、適宜マットの交換をしましょう。⑧幼虫が蛹室を作り始める(蛹化)この時期が近づくとサナギになる部屋『蛹室』を作ります。蛹室は壁面を利用して作ることが多いので、きれいに作った時は成虫になるシーンを観察することができます。種類により蛹室を縦や横に作る。この蛹室を作るともうエサは食べません。蛹室を作って数週間するといよいと蛹化が始まります。この蛹化の瞬間が、一番デリケートな時期です。⑨蛹になる成虫になる前段階がサナギです。この時期が近づくとサナギになる部屋『蛹室』を作ります。蛹室を作るともうエサは食べません。蛹室を作って数週間するといよいと蛹化が始まります。この蛹化の瞬間が、一番デリケートな時期です。蛹室は壁面を利用して作ることが多いので、きれいに作った時はサナ成虫になるシーンを観察することができます。種類により蛹室を縦や横に作ります。蛹になったらできるだけ騒音のないところに置いたり、動かさないようにします。⑩羽化(うか)掘り出し蛹が成虫に脱皮することを羽化と言います。羽が完全に固まるまで数日かかるのでさわらないようにします。
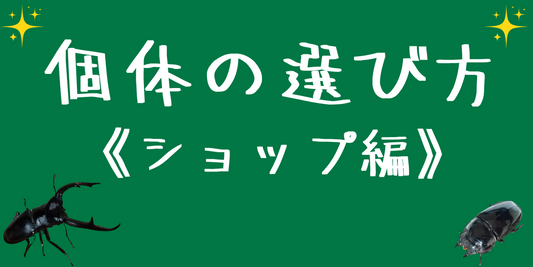
《個体はどれでもいいの?》
カブトムシ・クワガタムシは寿命、大食漢、よく動きまわる、産卵数、孵化までの期間、幼虫期間など種類により異なります。また産卵数など個体による差もかなりある虫だと思ってもらってよいです。 選ぶポイントは手や木にしっかりとしがみつけるか?腹部など大きな穴が空いていないか?足などが切れたりしていないか?野外採集品はいつから活動していたか分からず、寿命もわかりません。体にキズがついているものもあるが、元気であればほとんどは大丈夫。足が切れている虫でも元気であれば産卵にはあまり影響はないと言われています。体に傷があったり足が切れていても、元気であれば産卵にあまり影響はないことが多いですが、時間の経過とともに符節が取れやすくなるといわれているので、寿命の観点から購入はなるべく避ける方がよいと思います。購入の前に昆虫ショップ、またはオンラインショップでもそのお店が信頼のおけるお店なのか調べてから購入しましょう。初めて飼う人にとっては、何をどれくらいの量のエサをあげればよいか、どんな世話をするのか、疑問点がたくさんあるのではないでしょうか。今では多くの情報が公開され飼育に役立てられるようになってきました。さあ今からカブト・クワガタの飼育方法について一緒にみていきましょう!カブトムシクワガタムシは体が丈夫で乾燥に比較的強い種類もいますが基本的には乾燥に弱い生き物です。ケース内が乾燥していると身体の水分も飛びやすくなります。エサは水分を補う方法でもあるのでエサを切らすことがなければ、そこまで問題がないかもしれません。水分を補いたいのでケース内をよく動き回り体力が奪われることがあります。

《カブクワ飼育ブログ開設します》
私が子供の頃、もちろん外国産の昆虫は飼育した経験がなかったですし、国産オオクワガタの飼育することもなかなか敷居の高いものでした。材飼育とは、朽ち木の中に幼虫を入れて、長い期間かけて幼虫を羽化させるものです。現在マット飼育では、菌糸ビン飼育と一緒にカブト・クワガタを自宅で羽化させることが容易になりました。しやすい虫の代表とも言われるカブトムシ・クワガタ。飼育に必要な道具も用意しやすいので、虫の飼育初心者でも始めやすいです。いえ今のように暑い夏、日中離れる時、室温も高いからそんな状態でも大丈夫なのか?冬はどうなるの?とか、疑問がたくさんです。「カブト・クワガタに興味があるが、どうやって飼育したらいいのかわからない」 「どの虫なら飼いやすいの?」「繁殖させてみたい」などカブクワブログ飼育では、飼育に関して必要なもの、飼育のお悩みに丁寧に思っています。少しでも、皆様の飼育のお手伝いが出来れば幸いです。 日々の飼育に関する情報を配信していますので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。


